昨今、麻雀が静かに、でも確実に盛り上がりを見せているのを肌で感じます。
Mリーグや雀魂など、ライト層の入り口として優秀なコンテンツも増え、各所で麻雀というコンテンツが取りざたされているのを見かけます。
本当に、いい時代になったなぁと思います(しみじみ)。
どんな趣味にも言えることですが、コミュニティって「一部のディープ層」と「大半のライト層」でできてるんですよね。
麻雀も例外ではなく、今まさにこのライト層がどんどん増えてきてる印象です。
そして、麻雀を始めて少し慣れてくると、リアル麻雀欲が表立って出てくる瞬間があると思います。
「CPU戦じゃ物足りない」「実際の牌を触って打ちたい」
そうなったとき、仲間内のセット麻雀もいいですが、思い立ってすぐにメンツを集めるのはなかなか難しいもの。
そんなときに頼れるのが、フリー雀荘です。
とはいえ、「フリー雀荘ってどんな場所なんだろう?」「初心者が行っても大丈夫?」
そんな不安があるのも当然です。筆者も最初は、足がすくんで扉の前で引き返したクチです笑
だからこそ、この記事では「初めてフリーに行ってみたい」「雀荘は初めてだけどどんなところか知りたい」「一回友達といったけど、一人で入ってみたい」というあなたに向けて、事前に知っておくと安心な知識やマナーを詰め込んでお伝えしていきます。
この記事が少しでも背中を押せたら、そして願わくば、あなたがフリー雀荘の楽しさにどっぷり肩まで浸かってくれたら、筆者としては大満足です。
ではさっそく、フリー雀荘ってそもそもどんな場所なのか? 見ていきましょう。
フリー雀荘ってどんなところ?

フリー雀荘とは、知らない人同士で卓を囲んで麻雀を楽しめるお店のことです。
「1人でふらっと行って麻雀が打てる場所」と聞くとびっくりするかもしれませんが、実際は思っているよりずっと気軽な場所だったりします。
まず大きな分かれ目として、「ノーレート」と「オンレート」の2種類があります。
- ノーレートフリー:お金のやり取りなし。純粋にゲームとして麻雀を楽しみたい人向け。初心者歓迎のお店が多い。
ただし若干独特な雰囲気がある場合も。 - オンレート雀荘(一般的なフリー雀荘):点棒にレート(価値)がついていて、勝敗に応じて金銭のやりとりがある。いわゆる「普通のフリー」はこちら。
よく聞く「点5(テンゴ)」「ピン」などは、このオンレート雀荘でのレートの種類を指します。
「お金が関わるのはちょっと…」という人でも、ノーレート雀荘なら気軽に挑戦できますし、最近はそうしたお店も増えてきました。
「レートとお金の話」については別記事を作る予定
👉 フリー雀荘にはいくら持っていけばいい? レートと金銭感覚について(※記事が完成次第リンク予定)
お店選びは超重要!
フリー雀荘にもいろいろなお店があり、雰囲気やルール、客層もさまざまです。
最初に入るお店選びは、ちょっとだけ慎重にしたほうがいいかもしれません。
初心者向け・Mリーグルール対応・ノーレート専門など、自分に合いそうなコンセプトのお店を探してみましょう。
X(旧Twitter)などでお店の雰囲気を確認しておくのもおすすめです。
もし知り合いにが行ったことのある雀荘があれば、紹介してもらうのもオススメです!
リアルな話が聞けるのと、店によっては紹介特典があります。
個人的にはマーチャオに行くのがいいのではないかと思います。
・全国展開していてルールが統一されていて、オーソドックスかつシンプル
・お店がキレイで、接客もきちんとしている
・複数レートがある(店舗による、筆者のよく行く名古屋駅前店だと0.2~ある)
・最大手なのでお客さんが多く、待つことが少ない
・マナーがきちんとしている
と初心者に優しい要素が揃っていることに加え、
ある程度慣れてきたら、より刺激的なレート(婉曲表現)で打つこともできます。
セットなどで、祝儀が多いルールなどを打ちなれている人も、一旦ノーマルよりなマーチャオなどのお店に行ってから
違う店に行くことをオススメします!
フリーデビューで迷ったら「マーチャオ」へ行こう!
なにはともあれ、気軽に行ける場所!
「フリー雀荘」って名前だけ聞くと、ちょっと怖そうなイメージを持つ人もいるかもしれません。
でも実際は、店員さん(メンバー)も常連さんも、初心者に優しいお店が多いです。
点数計算やマナーについても丁寧に教えてくれるお店がほとんど。
誰でも麻雀を楽しめる場所が、現代のフリー雀荘のスタンダードになりつつあります。
とはいえ、知らない人同士で打つからこそ、ちょっとしたマナーがとっても大切。
ここからは、最低限押さえておきたいフリー雀荘でのマナーについて見ていきましょう!
入店〜着卓まで

「フリー雀荘に入る」って、それだけでもちょっとドキドキしますよね。
でも実際は、知ってさえいれば全然怖くないので、安心してください!
基本的には入店すれば、お店の店員さんから声をかけてくれます。
「初めて」とはっきり伝えるのがベスト!
見栄張って経験者ぶらないようにしましょう。
ルール説明などを省かれてしまいますし、ちょっと打てばフリー経験がないのはどうせすぐバレます笑
店ごとのルール説明はしっかり聞くようにしましょう。
特に三麻は要注意で、三麻はハウスルールが非常に多いです。
抜きドラは北を抜くのか、華牌を使うのかや、
赤が何枚あるのか、特殊役は何が採用されているのかなど、様々な差がお店ごとにあります。
フリーが初めてであれば、チップのやりとりについても聞いておきましょう。
基本的には、一発、裏ドラ、祝儀牌(マーチャオでは青)、役満などが祝儀対象です。
店によっては白ポッチや、金牌、そのほかいろいろなルールがあります。
ルール説明を受けたら、両替をして待機となります。
待機中ですが、基本的に何しててもOKですが、打っている方の後ろ見は基本NGなのでしないように注意しましょう。
対局中に気をつけたいこと
お店のルール説明を受け、いよいよ対局です。
フリー雀荘は「知らない人同士で打つ場所」なので、セット麻雀と同じように打つというわけにもいきません。
でも安心してください。特別な技術や礼儀作法が必要ってわけじゃありません。
簡単に紹介していきます👇
ちょっと多いけど頑張りましょう!
会話・発声に関するマナー
・まずは「よろしくお願いします」
卓についたら、まずは挨拶をしましょう。
初めてであれば「フリーは初めてです」もしくは「不慣れなのでご迷惑おかけするかもしれませんがよろしくお願いします」など、一言いっておくと助けてくれる率が上がります!
自分も体感的に、何も言わずいろいろできない人よりも、かなり印象がいいので言っておくのをお勧めします!
・発声は明瞭に
立直やロン、ツモ、ポンなどの発声は必ず明瞭に行いましょう。
卓内の全員にちゃんと聞こえるように。
実際に聞こえなくても、倒牌(ロン、ツモ)や牌を曲げる(立直)のアクションがあればトラブルになることはほぼありませんが、過去に数回、ロンと言ったけど聞こえておらず、かつ倒牌が遅くなり次の人の打牌まで終わってしまってチョンボと裁定され揉めたのは遭遇したことがあります。
無用なトラブルを避けるためにも、発声は明瞭にしましょう!
・鼻歌・放歌の禁止
鼻歌を歌う行為は禁止です。
表向きの理由は、大きい声を出すと他の卓だったり同卓者に迷惑が掛かるから。
同卓者の発声が聞こえにくくなったりで、トラブルになりかねないからですね。
本質的な理由としては、通しと呼ばれる、自分の必要牌などをサインで教え合うイカサマの防止のためです。
あとは、負けてしまっている人には煽りと捉えられかねないのも理由にあると思います。
・他家のアガりや打牌などに対する発言
アガリ批判・打牌批判などは当然厳禁です!
また、局終了後に「これ危ないと思って止めたんだよねー!」みたいな誰も求めてない解説もどきもNGです。
あんまりデビューでこれやる人はいないと思いますが笑
・長考の際は「失礼します」
もちろん「すみません」程度でも大丈夫です。
ともかく一言掛けましょう。全然印象が違います。
何秒からが長考かというのはプレイヤーによって全然違いますが、個人的な感覚でいうと3秒止まっていたら小考入れている、5秒も考えていれば長考しているイメージです。
フリーにまだ行っていない方は、Mリーグやプロなどの放送対局の感覚で毎巡のように考えるのは控えましょう。
牌の扱いに関して

・強打の禁止
牌を切る際に強く「バチン!」と切ったり、ツモアガリの際に叩きつけるのは厳禁です。
また、ツモアガリの際に卓の枠に当てる「引きヅモ」も同じく厳禁です。
相手への威圧になるという精神的な理由と、
卓や牌が傷つく可能性があるという物理的な理由です。
正直漫画やMリーグなんかでも度々見かけますが、実際のフリーマナーとしてはNGです。
あれはエンタメなので・・・
・先ヅモの禁止
上家の人が打牌を完了する前に、牌をツモってくることを「先ヅモ」といいます。
副露が入った際などに、牌が見えてしまい、不公平なので絶対にやめましょう。
また、手牌に入れてしまって不要牌を戻す不正もできてしまいます。
・開局時には山を前に出す
配牌を空ける前に、自分の前の山を少し前に出してください。
デフォルトの位置は対面からツモりに行くにはやや遠く、取りづらいです。
牌山の右側を少し奥にして斜めになるようにすると望ましいです。
王牌の場合は逆に左側が前になるように出してください。
これは次に同卓者がツモる際に、牌を引く側が前に出ていないと、下山に牌が残っているかが視認しづらく、
間違えて次の人のツモ牌を取ってしまう可能性があるからです。
実際にフリーに行けば王牌も右前に出す人の下家に座ることがありますが、割と牌山の奥の下山は見にくいです。
いわゆる「井桁に組む」言われる行為です。
なお四麻では嶺上牌をおろすのがマナーですが、三麻ではこれはしません。
華牌もあり、嶺上牌を取る機会が多いためです。
山の牌に関してですが、他の人の前の山にはツモ時以外には触れないようにしましょう。
カンをした際の新ドラめくりや、何かの際に牌がこぼれたときに手を伸ばして直す人、
ひどい人だと、牌が引きにくいからと両手で他山の位置を勝手に変える人などいますが、
絶対にやめましょう。
・基本は利き手のみで牌を扱う
基本的には利き手でツモってきて、利き手で切ります。
左手で引いてきて、右手で打牌、みたいなのはNGです。
両手を使うときは、アガリなどの倒牌のとき、理牌のときくらいで、
基本的に左手は卓の上に出さないようにしましょう。
・打牌前にツモ牌を手牌の中に入れない・手牌の上に乗せない
初心者にありがちなやつですが、ツモった牌は手牌の右端に置き、先に打牌をしてから手牌に入れるようにしましょう。
打牌忘れで多牌になる原因になる他、手出しツモ切りという公開情報がわからなくなる、
万一アガリであれば、アガリ点が変わってしまうケースがある、などの理由からです。
また、放送対局で見かける(多分今はほとんどないですが、かつてのMONDO対局などはやっていた)
ツモってきた牌を手牌の上に乗せる行為ですが、あれはカメラに見せるための所作なので、フリーであればやらないほうが無難です。
落としたり、磁石の関係でくるっと回ってしまったりで、他家に見せてしまう原因になります。
・6枚切り
捨て牌は1列に6枚切ったら、次の列に切るようにしましょう。
これ以上長いと、両サイドのプレイヤーの捨て牌とぶつかったりして、切りにくいですね。
今の雀荘にある自動卓であれば、多くの機種が6枚で切っていくとサイコロボックスの幅とおおよそ一致し、
6枚で切ると見栄えが良くなっているので、自然に6枚切りになると思います。
立直時のマナーについて
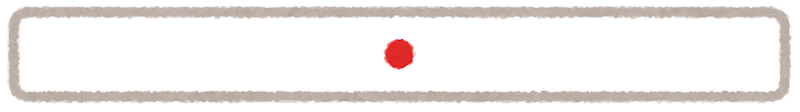
・立直発声→打牌→1000点供託の順に立直宣言をする
立直の宣言が後だと、自分の宣言牌に鳴きが入らないことを確認しての後出し立直が可能になってしまいます。
また立直を受けた側も、立直なら鳴くという判断をとることもありますので、必ず先に「立直」と発声してから打牌をしましょう。
また、1000点棒は打牌後に供託しましょう。
宣言牌がロン牌であった場合に、1000点棒を戻すという無駄な動作が発生します。
上がってないのに供託を持って行っているようにも見え、点棒授受の間違いの元になりますので、こちらも守るようにしましょう。
・手牌を伏せない
立直後に手牌を伏せて待機する人がいますが、これもやめましょう。
上がったときに倒牌をしづらいですし、起こす際に手牌や山牌を崩してしまう可能性を上げるだけで、伏せる意味は皆無です。
自分の上がり牌の確認や、カンの判断などで、手牌が見えるほうが明らかにいいです。
当然なんですが、立直時以外にも手牌を伏せるのはやめましょう。
テンパってるアピールになってしまい、三味線という明確な違反行為です。
また、牌の乱れを直すために、一度伏せる方もいますが、これもマナー違反なのでやめましょう。
手牌を手前にでも倒す行為をする時点で、アガリなのかと他家に勘違いさせてしまい、ゲームの進行を止めてしまいますし、そもそもアガリを誤解させることで明確な威嚇行為です。
・ツモ牌を手牌につけない
対局中マナーの先に打牌をするのと、おおよそ同じです。
手牌につけると、もしかしたら入れ替えてしまっていると勘違いされかねませんのでやめましょう。
一瞬なら大丈夫と思うかもしれませんが、小手返しなどで瞬間的に手出しにできてしまうので、疑われるような行為はやめましょう。
・立直後だからといっていろいろ見ない
これもセットとかだと、裏ドラを先に見たりとか、他の人の手牌を覗いたりといったことも許されるかもしれませんが、
フリーではがっつりマナー違反です。
やめましょうね。
副露(鳴き)時のマナー
・(ポン)副露の手順
ポンの際は、
ポンの発声→鳴く対子の晒し→打牌→拾牌→面子を右側に晒す
が望ましいです。
鳴く対子の開示は必ず打牌前にしましょう。
晒し間違えなどの際、打牌が完了していると戻せないので、ペナルティーが重くなります。
競技であれば打牌と拾牌は逆で、先に牌を持ってきて面子を完成させてから打牌のほうが正しいと思います。
ただフリーでは先に打牌のほうが、テンポがいいのでこちらを推奨します。
確かに打牌が先だと、鳴きが連続した時にややこしくなりますが、その時は一拍置いたり、先に牌を拾ってきたりと臨機応変に。
この辺はお店の雰囲気で決めたほうがいいかもです。
・カンの手順
カンの発声→手牌の槓材を開示→新ドラめくり→嶺上牌ツモ→打牌→拾牌→面子を右側に晒す
が実際のフリーではベストかなと思います。
拾牌についてはミンカンのみです。当たり前ですが。
こちらも競技の手順とは違うかと思います。
今回はオーソドックスなルールのマーチャオ想定で新ドラは即めくりを想定して、開示の後にめくっています。
新ドラが後乗りの店の場合は打牌後にめくりましょう。
また、新ドラは王牌の前のプレイヤーがめくりましょう(カンをしたプレイヤーが必ずめくるというわけではない)
抜け席の場合はなんとなく両脇のどっちかのプレイヤーがやりましょう。
細かい注意点ですが、暗槓の場合は祝儀牌(マーチャオでいうと青5)を見えるように通常の赤5を裏返しましょう。
上がったときに祝儀の数え忘れを防げます。
・抜きドラについて
大体カンと同じです。
手牌の華牌や北を右側に晒して、同じ枚数分嶺上牌から補充します。
慣習として、発声はなく、複数枚あるときは同時に抜いて、嶺上も複数枚同時に持ってきます。
ネット麻雀だと「ぺーにゃ!」とか謎の発声があったり、1枚づつ抜いたりなんで一応。
これは人によりますが、第1ツモの時に一緒に嶺上も引く人もいます。
個人的には多牌や少牌のリスクが少しだけ増すので、あまり推奨していません。
アガリ発生時のマナー

・発声について
「ロン」「ツモ」以外の発声は基本的にあまりよく思われないと思ってください。
もちろんある程度仲良くなったお客さん同士だったり、そういう雰囲気の雀荘だったりで許されそうならいいですが、
今までセットしかしてない方とかフリー未経験だと、「すげえ煽り方するじゃん・・・」って発声がたまに見受けられるので、「ロン」「ツモ」以外のアガリ発声は気を付けましょう。
別に「です」はつけてもいいと思います。
代表的な変な発声(その他所作)としては、
「御無礼」、「それ(ロン)」、「出るかね」「引くかね」など上がれると思わんかった系の発言、「高目(安目)」、「デバサイ」、無発声、ロンの際に牌を指さす行為・・・などなどがあります。
全部煽りと思われても仕方ない行為・発声です。控えましょう。
・両手で倒牌
両手で倒すようにしましょう。
裸単騎のときも両手でやれと言われますが、まあ1枚倒すだけの時は煽りっぽくならなければいいんじゃないでしょうか。
・理牌してから倒牌
ツモにせよロンにせよ、理牌してから手牌を開けましょう。
1枚程度ならいいですが、それくらい並べておきましょう。
確かに実際打つときに理牌しないのは、理牌の並びを読まれないために、意味がないことはないですが、
そこまでぐちゃぐちゃにせんでも、そんなに完璧に読み切れません。
倒したときに、同卓者がぱっと見で分かりやすいよう、並べてから倒牌しましょう。
あと理牌せずに倒牌すると、イキリだと思われるのでよく思われません笑
追記













上記の様な感じで、ごちゃついた部分を抜き出して倒す人をたまに見ますが、
数字の順番は崩さずに理牌しましょう。
ある程度麻雀に慣れている人ならわかると思うのですが、
33234345と並べられるより、23333445と並べられたほうが圧倒的に牌の並びがわかりやすいです。
なんなら54433332でもこっちのがマシです。
数字の順番が揃ってないと、例えば実は七対子の変則多面張だったりを見逃してしまうようなケースも想定できます。












例えばこんな風に並べていて、アガられたときにぱっと待ちや打点を把握するのに戸惑いますよね。
理牌すると












なので、待ちは6p1s東の変則三面張です。
アガリ牌によって手役も大きく変わってきます。
同卓者が見やすいことと、不慣れを見抜かれて風下に立たされることもあり、きちんと並べましょう。
・ツモ牌を手牌に入れない
立直後のツモを手牌につけないのと同じ理由です。
アガリ牌が何かで打点が変わるケースがありますので、右端に置いたままにしましょう。
・点数申告に関して
大前提ですが、上がった自分が申告します。
四麻では、アガリ点のみを申告することがグッドマナーとされますが、
三麻はドラなどが多くパッと見で打点がわかりにくいので、手役の申告をしてから打点を申告することがよしとされる場合が多いです。













上記のアガリでドラが7s、一本場、一発でツモで裏ドラは8pで1枚乗ったとしましょう。
四麻では「4100ー8100の2枚(です)」とだけ申告するのがよしとされますが、
三麻では「立直、一発、ツモ、中、一盃口、ドラ2、裏1で倍満一本場の2枚」と申告することが望ましいです。
私は「リーソクヅモチュンペコ2ウラ、倍満一本場の2枚です」と申告します。呪文じゃないです。
ちなみに上の通り、三麻は点数で申告するよりも、満貫、跳満などといったほうがいいです。
例えば6000-10000の時に、倍満ツモなのか跳満の2本場なのかで混乱するからです。
余談ですが、不慣れだと結構数え間違いを起こします。
ある程度慣れているプレイヤーでも普通にあることです。
人によってはほかプレイヤーが倍満を跳満と過少申告してしまった際、正しく指摘をすると不利益になる場合は正さないプレイヤーもいます。
(理想論は全員で正しく指摘するのがのぞましいですが、オンレートであればお金に直結するので、自己責任というのも正しい一種の考え方です。)
こういったときに、最初に言った「不慣れですが、よろしくお願いします。」の一言があると、正してくれる率がかなり上がります。
お互いの気遣いの領域なので、心穏やかにプレーできるように、一言は大事なのでいっておきましょう。
・点棒(チップ)の払い方
まず大前提ですが、相手のアガリと申告があっているかを確認しましょう。
また、フリテンなどのアガリが認められないケースがないかも一緒に確認しましょう。
余談ですが、ぱっと見て把握できる能力がないと、結構ごまけます。
面ピン即ツモ表赤裏とかでしれっと12000オールの2枚とか言われて、ちゃんと数えないと損しますからね。
点棒の払い方そのものの注意点ですが、必ず「相手の手元、卓の四隅に点棒・チップを置いて払う」ということです。
卓の中央部などに置いたり、当然ですが投げつけたりはNGです。
理由としては、中央に置くと牌を落とすことが出来なくなることと、複数人が払った場合に誰から来た点棒かがわからなくなるからです。
また、卓のエレベーター部分(牌が上がってくる場所)に置くのも、誤って次局の準備で卓を動かしてしまった際に詰まりの原因になるので、そこにも置かないようにしましょう。
あとは、どうやって払うかって部分です。
四麻でも言われますが、基本は、
・立直棒(1000点棒)が手元に残るように払う
・卓上に出す点棒の総数が少なくなるように払う
この2つを意識すればOKです。
例えば、東1局に立直を掛けた親が倍満をツモったとしましょう。
12000オールなので、あなたも12000点払うことになります。
もちろん1万点棒と1000点棒で払うのが間違いではありませんが、もう一人のプレイヤーがその払い方をしていたら、1万点棒と5000点棒で払うとスマートです。
親はもう一人の2000点と回収した立直棒合わせて3000点をあなたにお釣りとして返すことで、和了者は新たに点箱から1000点棒を出さずにお釣りを渡すことができます。
ちなみに祝儀(チップ)も点棒と一緒に払います。
店とか面子によってはオーラスの時は最後の精算時に一緒に払う方もいるので、漏れがないか確認しましょう。
あと、お釣りがあるときは「2000バックです」みたいに一言添えると、もらい忘れを防げるのでgoodです。
・点棒、チップをしまい次局へ
フリーという前提であれば個人的推奨としては、オーラス以外はしまうのは後にして、点棒チップは隅に置いておき、先に次局へ入る手順です。回転効率がいいので推奨しています。
第1打を切ってから点棒とかチップとかをしまえば進行の妨げになりません。
ただ、そこを良しとしない方も多分いるので、素直に点棒やチップをしまい、卓上がきれいになったら牌を落として次局へってのも、非マナーというわけではありません。ただ、意外と時間かかります笑
ちなみにサイコロボックス部分で牌を落としたり、逆に牌を上げたりしますが、基本的には次局に親をやる方が操作するのが望ましいです。
負けてたりで急く気持ちも分かりますが、急いで落としたり、勝手に次局に入るなどはNGです。
また、逆に「それ止めたわー」とか「○巡目にこうこうこう言う理由でこっち切ったら裏目ってうんにゃかんにゃ・・・」などどうでもいいことを喋って局を止めるのもやめましょう。
アガリの確認をして、点棒授受が済んだら、速やかに次局へ移りましょう。
代走に関して
代走とは
メンバーが電話やトイレなどで一時的に抜けるお客さんの代わりに、卓に入って打つことを「代走」といいます。
「ピンチ」と言ったりもします。
表向き、代走時メンバーは「普通に打つ」ことになってますが、店や人によりますが、全体的に「守備より」に打つ傾向があります。
極端な店だと、「立直、鳴き、といったアクションは厳禁」「相手の攻撃には必ずベタオリ」などの決めがあるケースもあります。(マーチャオは基本的に自由に打ってくれます)
ここはおそらくの話ですが、なぜ守備的になるかというと、代走中に放銃になるとお客さんが怒るケースがあるからかと思います。
代走を頼むときは、近くのメンバーに「代走お願いします」などと伝えて交代すればOKです。
席を外してからお願いしたり、無言で席を立ったりなどは論外なので絶対にやめましょう。
店の状況によっては代走に入れないケースがあります。
代走で何が起きても「ありがとう」を
代走をお願いして、戻ったときは何が起きていても「ありがとう」と言って卓に戻りましょう。
上で放銃したら怒るお客さんがいるといいましたが、論外です。
役満のダブロンに放銃していようが、チョンボしていようが、多牌していようが、何が起きていても
戻ったら「(代わってくれて)ありがとう」と声を掛けましょう。
リーチ代走がおススメだゾ
リーチ代走はその名の通り、立直を掛けた状態で代走をお願いすることです。
立直後は打牌選択などがなく、基本的には誰がやっても同じなので、結果でもやもやするのであれば立直代走にしましょう。メンバーさんも悩んだりせずに済むので負担が少ないです。
ただし次の点には注意してください。
・フリテンリーチなどの際はできるだけ頼まない(フリテンリーチありの場合)
待ち確認などはきちんと行いますが、メンバーさんは卓にきてササっと待ち確認などを済ませなければなりません。
フリテンなどは手牌だけ見てもすぐにわからないので、間違えてロンしてしまうことが考えられます。
フリテンリーチ時は自分でやるのが無難です。
・多面待ち時は自分でやるほうが無難
なんとも言えませんが、上で言った通りメンバーはぱっと見で待ち把握をする必要があります。
分かりにくい待ちの時は、メンバーさんが待ち把握に時間がかかることがあり、時間がかかってしまうと、
そこから複雑な待ちであることが透けてしまう可能性があります。
メンバーの雀力にもよるところはありますが、急ぎの用事でなければ自分でやるほうが無難でしょうか。
帰るとき
終了時には「ラスハン」コールを入れましょう
ラストの半荘にするって意味です。
半荘開始時に、これで終わりにする場合には「ラス半にします」とメンバーに告げてください。
時間次第で終わったり、(言わなくていいですが)金銭的にラスを引くと次に行けなかったりで、迷っている際は
「もしラス」という手もあります。もしかしたらラス半の意です。
ただしもしラスの場合、新しい来客があった場合には交代とさせられるケースもあるので、そこは気を付けましょう。
その他 よくあるQ&A
・フェアプレイの精神で
勝てばよかろうではなく、フェアプレイをしましょう。
例えば見せ牌(手牌や山の牌などを誤って同卓者に見せてしまうこと)や腰(鳴きを迷うモーション)といったものがあります。
例えばマーチャオなどはこれらの行為はノーペナルティとなっています。
だからと言って悪用は厳禁です。
鉄牌のジャンの様なプレーはやめましょう。漫画としてはめっちゃ好きなんですがね。
・トラブル時や同卓者に物申したい場合は、メンバーを通して言う
「発声が聞こえず次の打牌をしてしまった」とか「少牌をしてしまった」「間違えて立直を掛けてしまった」などなど進行上のトラブル、シンプルに卓の不具合などがあった場合にはメンバーさんを呼びましょう。
また、「同卓者の発声が毎回小さく聞こえない」「不必要に山を触ったり、カチャカチャやっていたり気になる」など同卓者のマナーに物申したいことはあると思います。
私もいっぱいあります。本当に。
そういうときも直接指摘せずに、メンバーにこっそりと伝えるようにしましょう。
トラブル回避になりますし、逆恨みで変に標的にされてもうっとおしいので。
・マジのガチで初心者だけど行ってもいいのか?
行ってもいいですが、正直おススメはしません笑
今は、三麻であれば符計算はほとんどの店でないと思うので、出来なくてもあんまり問題無いですが、
ちょっと複雑になるともう待ちがわからない、とか、役を全部覚えていないとかだと、進行が難しいです。
少なくとも麻雀ゲームとかアプリとかでは問題なく打てるくらいには慣れておいたほうがいいかと思います。
でも最初はみんな初心者なので恥じる事ではありません!
ある程度打てるようになったらどんどん雀荘に行ってみましょうよ

鉄牌のジャン! コミック 全7巻
鉄牌のジャン!全7巻完結 +サル!マネー!! を加えた鉄牌のジャン!ファンのための全8冊コレクターセット
打牌速度に関して
打牌の速さに関しては、下記の記事で別途解説しています。
せかせかする必要はありませんが、テンポよく打つのが理想です。
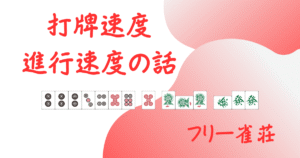
まとめ
・ほかの方と打つ場所なので、お互い不快な思いをしない様に良識ある態度を
逆に言えば、他の方が不快に思わなければ大体OK!
・何かあればメンバーさんに相談
・帰るときは「ラス半」を入れてからにしよう
・お店選びで困ったらマーチャオへ!
フリーには決して怖い場所ではないです!あまり怖がり過ぎなくてOKです
気軽に行きましょう!



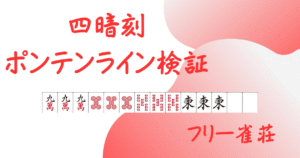

コメント