麻雀で勝ちたいなら、とタイトルづけましたが、麻雀に限らずすべてに通ずる話をします。
今回は「勝ちたいなら勉強が必要」というお話です。
あんまり麻雀の具体的な話は出ません。
勝負事で「勝つ」とはどういうことか

繰り返しですが、勝負事に勝ちたいだとか、投資で利益が欲しいだとか、結果を出したいのであれば勉強が必要です。
私も麻雀を初め、ポーカーだとか競馬だとか将棋、のボドゲから、FX、株、仮想通貨の投資などいろいろと手を出してきました。
始めてFXに手を出したのは大学生の時で、クリスマスに某フライドチキンチェーン店で圧倒的繁忙期にバチクソ働いて稼いだ2か月分の給料をものの1週間程度でほぼ溶かしました。
今となってはいい思い出・・・なわけも無く高い授業料でした(涙)
さて、一般論として試験や受験、仕事での出世争いなんかも勝負といえるでしょう。
私の経験則から「まちがいない!」と長井秀和ばりに断言できますが、なんとなくやっているだけでは勝てないってことです。
これはどんな勝負事にも言えると確信しています。
究極、じゃんけんですら、しっかり学んでいるのとそうでないのとでは勝率が変わると思っています。
自分の捉え方の話ですが、勝つというのは「数字を残す」ことだと思っています。
あくまで長いスパンで勝率を高め、結果を目に見える形で出すことが目的です。
いわゆる必勝法とか、ここ一番で絶対に勝つ方法、みたいなものを伝授できるわけではありません。
ただ、勝率が高ければ「ここ一番」で勝つ可能性も当然高いわけで、基礎がおろそかではいけないことはわかると思います。
具体的な勝率を高める方法
ようやく本題ですが、勝率を高める方法は以下を参考にしてください。
一応麻雀をメインに挙げています。
他の勝負事などにも参考になることは多いかもですが、必ずしも当てはまるかは微妙です。
1. 知識をつける
2. メンタル管理をする
3. 癖をなくして隙を与えない
4. 対戦相手を意識しすぎない
5. 違う分野に手を出してみる
6. 自分がアドバンテージを取れる相手から搾取する
って感じです。
6におっかないこと書いてありますが、究極これがすべてです。
結局自分が勉強したアドバンテージを活かして、相対的に自分より技術的に劣る人に勝利していくのが対人戦略です。
知識をつける
勝負事での勝利の土台はまず「知識」です。
やはり相手よりその物事に精通していない状態では勝率は下がってしまいます。
例えば漫画『ONE OUTS』の原作漫画4巻(アニメでは7~9話)のマリナーズ戦の話なんかは、どちらもルールの穴を知り尽くしているからこそ、相手の裏をかく戦いが成立していました。
え?非現実的? マア、ソレハソウナンデスガ(ボソボソ
簡単に説明すると、主人公「渡久地」が滅多打ちにされて相手のマリナーズに1回から大量得点を献上してしまいました。
しかしそれは渡久地の策略で、狙いは試合を遅延させ大雨による降雨コールドでのノーゲームでした。
狙いが見破られてからは、延々と牽制をしたり、ボークを連発するなど露骨に相手をアウトにしないように遅延行為を繰り返していきます。
それを受けてマリナーズも、バッターボックスから意図的に出たり、四球を受けて通常と反対の三塁に走って行ったりと、ルールの穴をつきなんとかアウトを貰って、試合成立の5回まで早く進めようとします。
要するに普段は起こり得ない、ルールブックの隅っこをつついて、攻撃側はなんとか攻撃が早く終わるように、守備側は得点をいくら与えてもいいからできるだけ引き伸ばしをできるかの戦いとなっていきます。
まあそのあとは渡久地の真の狙いもありまた展開は変わっていくのですが、言いたいことは「知識がないと一方的に虐殺されてしまう」勝負もあるということです。
・プレートを踏まずに投球するとボークになる
・バッターボックスから足を出した状態で打つと打者はアウトになる
・試合を進行させる意図がないとみなされる過度の牽制はボークとなる
など、普通に野球をしていても見ていても「そんなん知らんわ!」ってなるルールがルールブックには記載されています。
知識のない人がその場に入っても、何が起きているのか理解すらできず、勝負にならないでしょう。
本筋とはそれますが、この試合の詳しいあらすじはこちらのブログで紹介されてましたので良ければ見てみてください。
麻雀も同じで、例えば「アシスト」という戦術を知っているのと知らないのでは、打牌の方針も大きく変わりますし、
オーラスなどのトップ死守率などにも影響します。
アシストは非常に有用な戦術なんですが、それを知らずにその戦術を採れないのは非常に損ですよね。
だからこそ、まずは基礎的なルールや牌効率に加え、戦術の幅を広げる知識を学ぶことが「勝率を高める第一歩」になります。
あと『ONE OUTS』はマジで面白いから全人類読もうね。
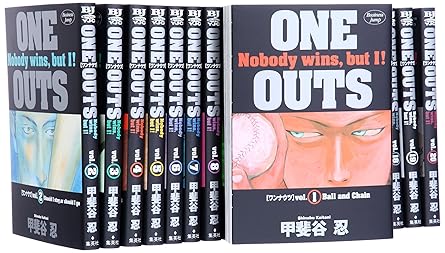
ONE OUTS 全20巻 完結セット (ヤングジャンプコミックス)
メンタル管理
例えばポーカー用語に「ティルト」という言葉があります。
意味としては「プレイヤーが合理的な判断をできなくなり、感情的な行動をしてしまう状態のこと」です。
麻雀で言えば、ラスや大物手での失敗で感情が揺さぶられ、その後の打牌に悪影響を与えることがあります。
リーチの不発が続いているのを気にしてしまい、立直判断が消極的になったり、
連続ラス後にいわゆる熱続行をしてしまったりなどと、普段やらないミスを誘発してしまうことでしょう。
ではそういう状態にならないために、どのようなことができるでしょうか。
休憩を挟む:感情が揺れたら一度手を止める、試合後やラスの後は一呼吸置くなどルールを作る
結果よりプロセスを重視する:勝ち負けより、「正しい判断ができたか」を検討で振り返る
自分のパーソナリティを理解する:自分がどのようなときに動揺するのか、判断がぶれやすいのかを知る
これは断言しますが、メンタルが揺れない人はいません。
ですが、対処法を知っていると、プレイのクオリティの低下は抑えられるかと思います。
こういったところを実践していけば、メンタル管理もできるのではないでしょうか。
以前、不運が続く時の対処法の記事も書いたので、良ければこちらも読んでみてください!

癖をなくして隙を与えない

自身の癖というのは勝負事ではキズになります。
野球やバスケなどのスポーツにおいてでは、投球時の癖などから球種がばれてしまったり、
ステップの踏み方からシュートフェイクを見抜かれてしまったり、といったことが起こり得ます。
上記のようなスポーツなんかは、身体を目いっぱい使うので、癖なども出やすいかもしれませんが、
麻雀などでも同じく、癖や所作から、手牌や狙いが見抜かれてしまうことがあります。
逆にそれを利用した読み(所作読み)なども可能です。
よくある麻雀での所作から読まれてしまうものとしては、例えば以下の様なものがあります。
・聴牌したらたばこを吸う いわゆるテンパイタバコ
・今まで朗らかにしゃべりながら打っていたのに、急に静かに河を凝視しだす
・牌をツモって来るときにそもそも上家、下家から見える
こういった所作は本当にフリーなどでもよく見受けられます。
そんなわかりやすい奴おらんやろと思うかもしれませんが、普通にいっぱいいます。
ここまであからさまではないにせよ、しっかり観察すると色々な「癖」があります。
こういうところをしっかりと観察してくる相手だと、自身の癖が傷になってしまいます。
麻雀では小さな癖や仕草の積み重ねが、長期的に勝率に影響してしまいます。
ちょっとした所作の差で、相手に有利な情報を与えてしまうこともあるので、意識的に防ぐことが重要です。
対戦相手を意識しすぎない
麻雀は運の要素が大きいゲームですが、その中でもやれることをしっかり徹底できるかどうかで、結果は大きく変わります。
例えば、自分が何度も上がっていて同卓者がつい溜息をついて明らかに嫌気がさしているのが見て取れるとします。
こういう時にもしっかりと遠慮せずにちゃんと立直を打ってカッパギに行きましょう。
ちょっと気まずいのは間違いなくそうですが、相手が上がりまくるときもあります。気にせず圧勝しましょう。
性格にもよりますが、案外遠慮してしまってできなかったりもします。
もちろん逆も然りで、例えば相手の所作なんかで相手にイライラしてしまったりというケースもあります。
そういう場合でも一呼吸おいて、落ち着いて集中しましょう。
ましてや直撃を取りたいからといって、通常なら立直する手をダマにするなどのプレーは収支に直結してしまいます。
麻雀は勝負事である以上、相手の様子や雰囲気に引っ張られることは避けられません。
ですが、相手を意識しすぎて本来のプレーを崩してしまうのは一番もったいないことです。
麻雀は自分の手牌を間違えないことが一番大切です。
自分のやれることを徹底することが、結果的に勝率アップにつながります。
違う分野に手を出してみる
勝負事での考え方などは、競技が違っても共通していたり、取り入れることでレベルアップしたりと、参考にできる部分が多いです。
例えばポーカーには「GTO戦略」と「エクスプロイト戦略」との、(基本的には)対になる戦略があります。
詳しく解説すると非常に長くなる・・・というか私の知識だとできないので、簡単に言うと以下の様な感じです。
- GTO戦略
-
Game Theory Optimal の略で、ダイレクトに訳すと「ゲームの最適理論」みたいな感じでしょうか。
理論上の行動のバランスが最適なプレイングをする。相手のプレイに影響されにくく、自分の損を減らして安定する選択肢。
- エクスプロイト戦略
-
相手のクセや弱点、損な行動を突いて利益の最大化を目指す戦略。
要は「相手のミスを突く」戦略。GTOが安定択とするなら、エクスプロイトは「攻め」の戦略。
相手のブラフが多いとみればコールを増やしていき、
逆にフォールドが多いプレイヤーであれば、自身がブラフを多用していく。
GTOでは取れない「上乗せ利益」を獲得できる可能性があるが、読み違いやレアケースなどのリスクがあり
(GTOと比べると)安定感に欠ける。
麻雀を打つ方ならこの「GTO」と「エクスプロイト」の関係が「デジタル」と「アナログ」の関係に非常に似ていると感じるかもしれません。
違う競技でも、似た考えが存在することはわかっていただけると思います。
上ではポーカーの例を挙げましたが、他にも例えば、投資関係であれば「損切り」の感覚は麻雀での押し引きやゲームメイクに活かせるかと思いますし、スポーツなんかの勝負勘や観察眼なんかも麻雀の読みに活かせます。
こうして別の分野に触れることで、自分の競技を客観的に見直すことができます。
様々な勝負事を横断して考え方を広げていくと、着実に自分の土台が強くなります。
麻雀で勝ちたいからと麻雀の勉強ばかりをするのも良いですが、たまには別のゲームや競技に手を出してみるのもおすすめです。
息抜きにもなってメンタル管理にも活きますしね。
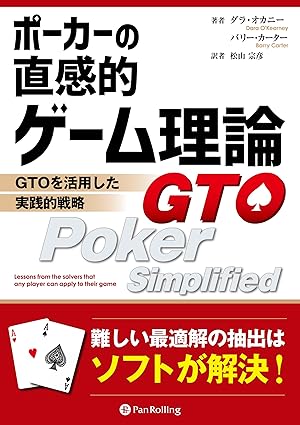
ポーカーの直感的ゲーム理論 ――GTOを活用した実践的戦略 (カジノブックシリーズ Vol. 33)
自分がアドバンテージを取れる相手から搾取する
勝負事で勝率を上げるには、自分が持っている知識や経験、技術といったアドバンテージを最大限に活かすことも重要です。
というか全員が勝てないゲームである以上、自分の利益はほかプレイヤーの不利益から出ているゲーム性です。
言葉を選ばずに言うと、どうにかして「自分より未熟なプレイヤーからカモる」か、ということです。
ズルく聞こえるかもしれませんが、対人ゲームなんか突き詰めれば大体こういうものです。
将棋なんかで、相手の仕掛けに対して、自分が定石を知らずに受けきれず劣勢になってしまうのも、乱暴に括ってしまえば同じです。
まさか、「自分が知らない定石を使って勝つなんて卑怯だ!」っていうプレイヤーはいませんよね。
麻雀で言えば、他者が失敗してしまう牌効率を自分だけが正しく理解していれば、他者より上がり率が高く出ます。
他者が難しいと言っている押し引きを正確に行えれば、局収支が良くなります。
そういった小さいアドバンテージを積み重ねて、他のプレイヤーに勝ち越していきます。
勝負事は結局、全員が同じルールで、限られたリソースを奪い合うゲームです。
だからこそ、無理に強者を打ち倒そうとするよりも、自分がアドバンテージを取れる領域で、確実にリターンを積み上げることが、
長期的な勝利につながっていきます。
まとめ
勝負事って、うまくいかない時ほど「センスがない」とか「運が悪い」とか思っちゃいがちですが、
結局は、やれることをきちんと積み重ねてる人が一番強いんですよね。
知識をつけたり、心を整えたり、違う分野から学んだり。
どれもすぐには結果が出ないかもしれないけれど、気づいた時にはちゃんと自分の中で形になっています。
焦らず、自分のペースで。
そして、たまに勝てた時には素直に喜びましょう。
その繰り返しが、いちばん確実な「上達」への道だと思います。
いい言葉が思い浮かびました。
「好きこそものの上手なれ」
なんだこの締め方。
それでは。


コメント