いろんな麻雀力向上のサイトや書籍で「配牌の方針」や、第一打に何を切るべきといういわゆる「配牌何切る」なんかはまま見かけます。
ただ実際には第一打以前にやることや思考しておくべきことなどが結構多くあります。
その辺紹介されているサイトはあまり見つけられなかったので(検索能力の問題かも笑)
自分のルーチンを紹介いたします。
当たり前といえば当たり前の内容ばかりなので、やれてないと結構損をしているかも・・・?
逆にしっかりと毎局できるようになれば、平均着順も上がってきます。
基本的には麻雀の成績の安定のためのルーチンの紹介です。
しかし実戦でこういったところでのミスを減らすことも、ちゃんとした上達の一部です。
もし初心者・初級者の方やフリー麻雀が不慣れな方で、意識したことのない方には、必ず体にしみこませてほしい内容になります。
一応基本はフリー麻雀想定での話になります。
とはいえ、ネット麻雀でも大事な思考なので、一読していただきたいです。
山を前に出すとか嶺上牌をおろす、みたいなリアル麻雀でのマナーとかとは別物と思ってください。
下記はフリー雀荘でのマナーを押さえた記事です。
少し長いですが、一読してからデビューするのがいいと思います!

点棒状況の確認
当たり前だと思いましたか?
おっしゃる通りで当たり前です。局開始時に点況の確認は当然です。
当然なので、テンパった時になって初めて、どこから上がれば条件を満たすかとか考えてないですよね?
まず!局に入る前に点棒状況の確認を!絶対にしてください!
正直これを伝えられれば半分くらい言いたいことはオッケーです笑
これやるだけで、平均順位0.05は上がります。本当に。知らんけど。
特に南入してからは必須です。
自分とトップの差は何点なのか。
誰に何点を放銃したら着順が落ちるのか。
トビ寸前(やコールド寸前)の人はいるのか。
特に三麻であれば東場のうちから、大きい手の横移動などで条件が発生するケースも頻発します。
繰り返しですが、配牌を見る前に現在の点況を再確認し、どういった方針で打ち進めるのかを認識したい。
満ツモを目指す局と倍ツモを目指す局では第1打(なんなら第1打以前にポンをするか)から判断が大きく変わります。
下の記事は私の実戦譜です。
ネット麻雀のものですが、点況を把握し、条件確認をしてうまくいった局の解説記事です。
良ければご一読ください。

ドラの確認
これも当然っちゃ当然ですね。
でも切った後「あっ!」って言って誤ってドラ切ってる人、まあまあ見かけますよね。
赤は目立つからいいんですけどね笑
ぼーっとしていたり、負けが込んでしまっていると、つい「早く早く」の気持ちになって、
こういった確認がおろそかになってしまうことがあります。
なんでこういうミスは、ルーチンを守ることで無くしていきましょう。
三麻であれば、牌理上一番いらない牌がドラであっても切ったほうがいいケースが多いですが、それは平場での話です。
当然、南入していて少し凹んでいるだとか、トビ寸前者がいて条件があるような局面では、ドラを活かす手組みをしたいところです。
特に字牌同士の比較であれば、数牌よりも「ドラだから」切るのを遅くする、または早くするというケースが多いです。
考えたうえでのドラ切りはもちろんOKですが、見落として切る愚は避けましょう。
鳴く牌の把握
一応上がり牌の把握もですね笑
余談ですが、フリーだと自分西家で親の第一打がロン牌だけど理牌が間に合わなくて、南家の打牌が完了していても、
巻き戻してロンできる店が多い気がします。
ただポンは戻れないので、即座に鳴きを入れる牌は把握する必要があります。

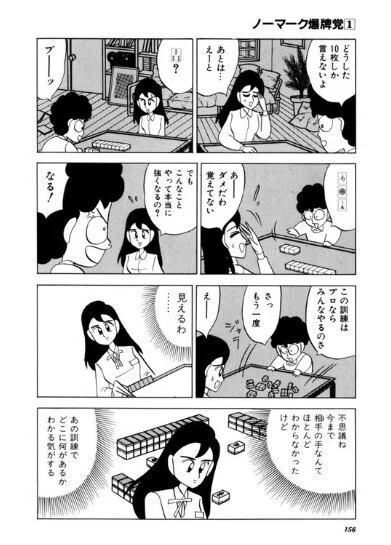
『ノーマーク爆牌党』にこんな特訓シーンがありましたが、割と近いかもしれません。
配牌をパっと開いて手牌の構成を瞬時に把握するのは必須です。

例えばこんな感じの手牌で役牌の中をスルーしてしまうと、かなり上がりづらい手牌で、自力で聴牌するのはおそらく12巡目以降とかになってしまいそうです。
逆に、中を1巡目にあっさりポンが出来れば、鳴きやすい対子が多くかなり速度感を挙げることができ、何なら3巡目くらいには聴牌を入れられそうです。
このように役牌対子の鳴き洩らしをしてしまうと、上がり率に大きく影響してしまう手牌もあります。
もし全部を見るのがどうしても間に合わなければ、役牌対子、字牌だけでも先に確認しましょう。
序盤(第1打前)から鳴きが発生するのは多くの場合役牌です。
マナー面との兼ね合いもありますが、瞬時に把握するのが難しいのであればできるだけ早く配牌を開けて、
視認するタイミングを早めましょう。
山を前に出したりしている間に、数秒とはいえ思考時間が増えて、少し余裕が出来ます。
(中級者以上向け)アガリ巡目の想定
出来ればでいいのですが、配牌を見て、自分の手が何巡目くらいに上がれそうかを考えます。
もちろん第1打以降でもいいのですが、最序盤の役牌鳴き判断などに多少影響してきます。
アガリ想定の巡目が早ければ、まっすぐ進めればいいですが、
明らかに先手を取れないであろう手牌の場合は、後手を踏む前提で手組みをする必要があります。
例えば、良形フォロー牌を引っ張り過ぎないとか、ターツ整理を早めにするといった対処が考えられます。
どちらにせよ、良形率や打点面で優秀な手組みをして、押し返せる手牌価値を作る、だとか
ダマケアも含め放銃にならないように安全牌を多く持つ、のようにまっすぐの手組みはできません。
不慣れなうちは難しいかもしれませんが、慣れてきたらこのあたりもできると成績が安定しやすくなると思います。
まとめ
・配牌前にできることはいっぱいある!さぼらない!
・点況の確認は必須
・役牌対子は見逃さない
以上が、特に初心者、初級者の方には必ず守ってほしい、第1打以前のルーチンになります。
たったこれだけですが、実戦で徹底できれば平均順位が大きく安定します。
「知っている」だけで終わらせず、今日から1局ごとに意識してみましょう。


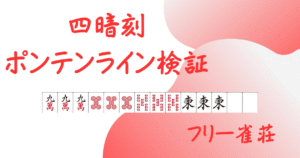

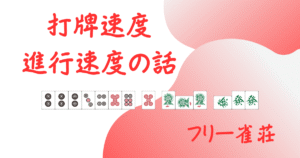
コメント